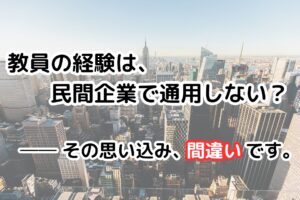どうも!こんにちは、1児の数学教師です。(^o^)/
今から限りある人生の過ごし方についての授業を始めたいと思います。
突然ですが、みなさんはスマホの充電残量が残り何%になったら不安になりますか?
私はその日の時間帯にもよりますが、60%台になったら「この残量で大丈夫かな?」と感じます。
そして不安になってくるのは充電残量が50%台ぐらいですね。
なぜこんな話をしているかというと、私たちの人生を80年とすると人生は4000週間(1年53週×80年=4240週間≒4000週間)です。そして私は今40代なので残りの人生は2000週間を切っている、つまりスマホの充電残量は50%を下回っている状態だということです。
自分自身を『充電することができないスマホ』だと思ってください。
もう自分自身を100%の状態にすることは不可能です。
人生を80年としたときに現在の年齢から残りの人生が何週なのかを表にまとめました。
| 現在の年齢 | 残りの人生 |
|---|---|
| 現在の年齢 | 残りの人生 |
| 20歳 | 3000週間 |
| 25歳 | 2750週間 |
| 30歳 | 2500週間 |
| 35歳 | 2250週間 |
| 40歳 | 2000週間 |
| 45歳 | 1750週間 |
| 50歳 | 1500週間 |
| 55歳 | 1250週間 |
| 60歳 | 1000週間 |
| 65歳 | 750週間 |
| 70歳 | 500週間 |
| 75歳 | 250週間 |
| 80歳 | 0週間 |
最近の世の中は”働き方改革”という言葉を筆頭に、仕事の効率化、ワーク・ライフ・バランスが叫ばれています。それに伴い、タイムマネジメント、タイムパフォーマンスという言葉をよく耳にするようになりました。SNSや書籍でも”いかに効率よくtodoリストをこなすか”という情報ばかりあふれていますが、私たちは自分たちの生活に余裕が生まれているということはありません。
だから、もっと生産性を上げていこう!、もっと効率的に仕事をこなす方法を探そう!ということを言いたいわけではありません。
そもそもの考え方を変える必要があるということです。
「完璧なワークライフバランス、やりたいことがすべて実現できるタイムマネジメント」なんていうものは存在しないという現実に目を向けることが重要です。
人生には終わりがあります。
歴史上、人の致死率は100%です。
当たり前ですが人生には終わりがあります。
あなたが今やっていることは自分のやりたいことですか?
自分に正直に『自分が何をしたいのか』を考えてみてください。
『自分が何をしたいのか』は、ある意味人生のテーマだと思います。自分のやりたいことに向かって計画建てて準備をすすめて目標達成までのこり2~3年だ、という人はそのまま計画通りに進めてください。
でもそうじゃない人は『自分が何をしたいのか』を真剣に考えてください。
そして残りの人生で何をして過ごすか、を考えるべきだと思います。
私が高校教員を目指した理由は教科指導(進学指導)がしたかったからです。
私自身が大学受験ですごく苦労したので、生徒たちに数学をわかりやすく教え、数学の楽しさや成績を上げる方法などを伝えたいと思っていました。だから大学4年生のときには、受験指導に特化している塾や予備校の先生も就職先の候補にありました。でも授業以外にも担任をしたり、学校行事を通して生徒を成長させたいという気持ちもあり高校教員を目指しました。
しかし教員になって勤務してきた学校は大学受験とは縁のないような学校ばかりです。教科指導よりも生徒指導が重要視されるような学校でした。当然、人事面談のときには進学校への転勤希望を出していましたが、それが実現することはありませんでした。
ある高校に勤務していたときに私をかわいがってくれていたベテランのA先生がいました。A先生が退職するときに”再任用で進学校に行けるのではないか”という噂が流れました。しかしフタを開けてみると、A先生の再任用先の高校は、教育困難校に属する学校でした。A先生はそれを受け入れていましたが、「1回ぐらいは進学校で教えてみたかったなぁ」と言っていた姿が印象に残っています。
申し訳ないですが、私はその姿を見て「自分の教員人生をそんな風には終えたくない」と思いました。そのときに公立高校を辞めて国立大附属で勤務することを決めました。
国立大附属の高校では学習意欲の高い生徒が多いので、自分のやりたかった教科指導や生徒の探究心をくすぐるような授業をすることができ、仕事における満足度はそれまでよりもはるかに上がりました。
それから数年後、子どもが生まれて、自分の人生をもう一度考えたときに私は自分の子どもとの時間を大切にしたいと思いました。変な表現になりますが、私にとっては”学校の生徒はよその家の子ども”です。よその家の子どもに時間を使うなら、自分の子どもに時間を使いたいと考えています。※もちろん勤務時間中は生徒と真摯に向き合います。
「子どもとの時間を大切にしたい」っていうのをもう少し踏み込んで考えてみると、子どもと色々な体験をする時間を一緒に過ごしたいと思っています。
具体的には
- キャッチボールやサッカー、バスケの練習を一緒にしたい
- キャンプに行って夜に一緒にカップヌードルを食べたい
- きれいな海でシュノーケリングを一緒にしたい
- スキーやスノボを一緒にしたい
とかです。
みなさんは自分の人生をどのようにして過ごしていきたいと考えていますか?
私は15年以上公立高校の教師として数学を教えていましたが、そのときの働き方に疑問を感じ、国立大附属高校に転職しました。今まで偏差値40未満の学校から偏差値70以上の学校に勤務し、5000組以上の生徒や保護者と関わってきました。子育てや家族のありかたは本当に千差万別です。そういったことを考える中で
- 教師として生徒との向き合い方
- 自分の家族との向き合い方
- 自分の人生との向き合い方
について考えさせられることも多く、「人生には限りがある」という当たり前のことを意識するようになりました。
私はもともと貧乏性でお金に対してケチケチしてるタイプでした。
しかし、結婚して子どもが生まれ、改めて自分の人生計画を見直した結果、家族で思い出を作ることにお金を使いたいと考えました。それからはお金の勉強をスタートし、ファイナンシャルプランナー、簿記などお金に関する資格を取り、NISAで投資をスタートさせました。また夜間の大学院に通い、自分の教員免許を専修免許にパワーアップさせ、大学院卒の給与体系に移行することに成功しました。
- 給与収入
- 資格手当
- お金の知識
- 配当金
のバランスをとりながら、年々収入を増やすことに成功しています。
今回の授業のテーマはこのブログのタイトルにもある【限りある人生の過ごし方】についての内容です。
お気づきの方もいらっしゃると思いますが、今回は『限りある時間の使い方』という本を参考にしています。この書籍を読み、それまで自分が考えていたことと一致する部分や新たな気づきを与えてくれた部分を紹介していきたいと思います。
●現実を直視する
この記事を読んでくださっている皆さんの中に、自分のやりたいこと(趣味や娯楽)、自分がやらなければならないこと(仕事や家事など)のバランスをとって時間を効率よく使えている方はいらっしゃいますか?他にも「24時間あれば十分に1日を楽しめます!」という方はいらっしゃいますか?
もしいらっしゃれば、お問い合わせフォームからその時間管理術を教えて下さい。
私は『限りある時間の使い方』を読むまでは、いかに効率よく仕事や家事を終わらせて自分の時間を作るか、を考えていました。でも勤務先の学校でも家でもなかなかそういった時間を作ることはできません。
しかし、この書籍を読んで、そもそも「効率よく仕事や家事を終わらせて自分の時間を作るか」という発想が間違っているということに気づきました。
ここからはみなさんに「ちゃんと現実を見ましょう!」ということを紹介したいと思います。
自分には限界があるという現実を受け入れて、「時間を作る」「時間をコントロールする」という発想を捨てましょう。
いつも時間に追われる理由
みなさんは勤務時間中のタスクや時間管理をどのように行っていますか?
わたしは1週間のtodoリストを作成し、
①緊急性の高いもの
②空いた時間に少しずつ進めるもの
の2つに分類して、授業の空き時間などを効率的に使うという工夫をしています。
この方法を取り入れてからは、短い空き時間ができたときに「今の空き時間で何をしようかな?」と考える時間がなくなり、効率的に時間を使えるようになったと思っています。
それでも気づけば勤務時間終了まで残り1時間を切っていることも多く、
・そのまま残業をするか、
・仕事はある程度切り上げて家に帰って家事を手伝うか、
の2択になります。
自宅に帰ってからも、子どもの食事をさせたり、一緒にお風呂に入ったり、夕食の後片付けをしていたら子どもの就寝時間まで残り10~30分しか残っておらず、子どもは「もっとお父さんと遊びたい」とグズりはじめます。その気持をなだめて、寝かしつけにいき、そのまま自分も寝てしまうのでそこで私の1日は終わります。
多くの人の1日のスケジュールもこんな感じじゃないでしょうか。
自分の時間はあまりにも短い。その事実を直視するのは怖いですよね。A, Bのどちらの選択(場合によってはA, B, Cの3択)をすれば効率的に時間を使えるのか、タフな選択は避けられません。
- やりたいことを全部やる時間はない。
- さらには限られた時間の使い方さえも自分ではコントロールできない。
- 時間以外にも体力や才能、スキル、その他いろいろなリソースが足りない。
- すべてを完璧にこなせる人なんていない。
上の項目って多くの人が納得できる内容じゃないでしょうか。でもそんな現実を直視したくないから、私たちは全力で現実と回避しようとして、
- 完璧なワーク・ライフ・バランス
- やりたいことがすべて実現できるタイムマネジメント
というような何の制約もないかのような幻想を追い続けます。
私たちは仕事でもプライベートでも「スケジュールを立ててそれを計画的に実行しよう(しなければならない)」という強迫観念にとらわれ過ぎています。
今回言いたいのはその発想を変えましょう!ということです。
ということです。
時間をコントロールしようと思って色々な時間管理術を試したとしてもそれはうまくいきません。みなさんも同じような経験はありませんか?
YouTubeやInstagramで流れてくる仕事や家事の時間管理術の動画を見て実践するけど、なかなかうまくいかず、むしろ時間のなさにストレスを感じてしまう。
私の周りではこういった人が多いように感じています。
時間管理術を手に入れて効率的に作業を終わらせるのではなく、未来をコントロールできないという現実を受け入れるという発想を持ってください。そうすることで不安が完全になくなるわけではありませんが、自分には限界があるということを受け入れれば、生活はもっと楽に感じますし、人生がもっと楽しいものになっていきます。
出来なかったことより、出来たことに目を向けましょう
もちろん不安が完全になくなるわけではないですし、”限界を受け入れる能力”にも個人差はあります。
ただ、現実を直視することが他の時間管理術よりも効果的だということは自信を持って言えます。
効率化ツールとの向き合い方
2020年のコロナ禍以降、部活動をはじめ、保護者対応や宿泊行事の引率などによる教員の多忙化が報道される機会が増えたように感じています。もちろん忙しいのは教員だけではないということは十分に理解しています。
ここで伝えたいのは、どんな経済的な階層の人たちや色々な職業の人たちもいつも不安と焦燥に駆られている、ということです。
・多額の住宅ローンの毎月返済
・給料は良いとしても、仕事が忙しすぎて家族とゆっくり過ごせない
・そのポジションを維持するための努力を継続しなければならない
・生活維持や子供たちを食べさせるために必死
・本業とは別でアルバイトなどの兼業をしている人は当然忙しすぎてクタクタ
・お金のことで夫婦げんかが絶えない
この2つの階層の人たちの問題は正しい時間管理術を身につけていないからではありません。もっと根本的な部分の認識を変えないといけないということです。
1日に詰め込めるタスクの量を増やしたとしても、仕事をコントロール出来る感覚は得られませんし、重要事をすべてやるだけの時間も生まれません。
そもそも何が”重要”なのかは主観に過ぎませんよね
「上司やチームにとって重要なこと」と「時間内に実行可能」かどうかは別の問題です。
それ以上に問題だと思うのは、多くのタスクをこなせばこなすほど、「あの人は仕事が早い」というイメージがついて、いろいろな方面から仕事を依頼されるということです。
みなさんも経験があると思いますが、なにか仕事をお願いするとしたら誰ですか?
・仕事が早いAさん
・仕事が遅いBさん
当然Aさんですよね。
皆さんの上司もアホじゃないので、仕事が遅い人に仕事を振っても期限ギリギリにならないと間に合うか間に合わないかの心配をするより、仕事が早い人に仕事を振って自分は自分の仕事に専念すると思います。
それに今まで勤務時間内に10のタスクを処理していたのを自分なりに工夫して12のタスクを終わらせたとしても、上司や周りから13個目のタスクを依頼されます。
またそれもさらなる努力で終わらせて定時に帰り、家で子どもとの時間や自分の趣味の時間を過ごしていたら、奥さんから別の家事をお願いをされる。
そんな経験はありませんか?
これは職場でのteamsやchatworkなどのチャットツール、家庭での食洗機や洗剤自動投入機付きドラム型洗濯機は作業効率を高めるために導入されたものの、自分の時間は一向に増えないという事実にもつながってきます。
今では誰もが持っているスマホやパソコンなどのITツールでは定期的にパスワードの変更を依頼される場面が多いです。私は細かいタスクを残しておくのが嫌なので、そういった指示がきたときはその場でパスワードの変更をします。
それなのに家族旅行の計画や白血病に罹った親友に会いに行くといった重要なことはいつも後回しになってしまいます。
現実を受け入れるというのは、すべてを効率的にこなそうとするのではなく、すべてをこなそうという誘惑に打ち勝つことです。
反射的にタスクをこなしたり「タスクを終わらせたい」という誘惑を振り切ってあえてやらないと決めることです。メールやチャットは次から次に届いて、多くのタスクには手がつけられなくて不安感や不快感を感じていたとしても、本当に重要なことだけに集中することです。
もちろん無理をして仕事をするようなときもあります。
ただそれを基本にはしません。
- いつかすべてが片付く
- いつか自分のやりたいことに専念できる
- いつか完璧な時間が手に入る
- いつか理想のワーク・ライフ・バランスで生活ができる
これらは幻想に過ぎないということを自覚しなければいけません。
これは仕事だけじゃなくて、人生にも当てはまります。
すべての楽しいことを体験することは不可能だということを受け入れていれば、他に楽しいことがあっても焦らなくて済みます。その中で自分が経験出来る数少ない体験を心から楽しみ、人生の限られた時間の中でやりたいことをもっと自由に選べるようになってきます。
「時間がある」というのは本当ですか?
みなさんは土日やGWなどの大型連休が終わるときはどんな気持ちでしょうか?
・有意義に過ごせた
・やりたかった〇〇が出来た
・家族とゆっくり過ごせた
とプラスの気持ちで終わる場合もあるでしょう。
一方、
・思ったほどゆっくり出来なかった
・お酒を飲みすぎて2日酔で1日潰してしまった
・仕事のことを考えると気持ちが沈む
など、マイナスの気持ちになることもあるでしょう。
それはなぜだと思いますか?
スウェーデン出身の哲学者マーティン・ヘグルンドは”有限性に向き合う”という考え方を次のようにわかりやすい言葉で説明しています。
宗教は永遠の命を説くけれど、もしそうだとしたら人生には何の意味もないのではないか。もしも人生が永遠に続くと考えるなら、自分の命が貴重だとは思わないだろうし、自分の時間を大切に使いたいと言う思いもなくなるはずだ
永遠の命があれば、日常は死ぬほど退屈になると思いませんか?
今日やらなくても、明日も明後日も永遠に日々が続いていくので今日何かをやる必要はありません。
もし夏休みが何度でも無限にやってくるなら、夏休みに特別な価値はありませんよね。
無限には続かないからこそ、子どものときも大人になってからも価値を感じるのです。
- 死が確実にやってくること。
- 自分が死に向かっていること
を見つめたとき、人はようやく本当の意味で生きることを知るのだと思います。
癌や大病を患った有名人の書籍やインタビューでは決まって闘病体験を”素晴らしい出来事だった”と語るのは、まさに人生の有限性に直面したからだと思います。
自らの死に直面したために、人生の見え方が変わり、あらゆるものが鮮やかな意味を持って立ち上がってくるのだ。死にかけた人がそれまでより幸せになるわけではない。そんな単純な話ではない。自分が死ぬという事実、そして自分の時間がとても限られているという事実を骨の髄まで実感したとき、人生には新たな奥行きが現れる。幸せというよりも、人生がよりリアルになるのだ。
こんな風に偉そうに”人生の有限性”について書きましたが、正直に言って私も自分の死を完璧に受け入れて、心安らかに日々を送っているわけではありません。というか、事故や大病を患って死に直面した経験のある人以外でそんな人はいないと思います。
ただ死を受け入れ、人生には終りがあるということを自覚して、生きる態度を少しでも変えることができれば現実の世界はそれまでとかなり変わって見えるはずです。
可能性を狭めることで、見つかる可能性
みなさんはタイムマネジメント術にまつわる『ビックロック(大きな石)の法則』を知っていますか?
『ビックロック(大きな石)の法則』という名前は知らないかもしれませんが、この説明を読めば何のことかわかると思います。
教師が教室に入ってくる。
大きな石をいくつかと、小石をひと握りと、砂のつまった袋と、大きめの瓶を持っている。さて教師は生徒たちに「ここにある大きな石と小石と砂を全部入れてみましょう。」と説明する。生徒たちはどうやらあまり頭が良い方ではないので小石や砂からどんどん入れていく。
すると大きな石が入らなくなる。
教師はそれを満足そうに眺めてから、したり顔でお手本を見せる。まず大きな石を入れる。次に小石を入れて最後に砂を入れなさい。
そうすれば、大きな石の隙間に小石がきれいに収まりますよ。
この『ビックロック(大きな石)の法則』で伝いたいことは、最も重要なことから手をつければ、重要ではないことも含めて全部終わらせられることが出来るという意味です。
逆の順番でやろうとすると重要なことをやる時間がなくなってしまいます。
これは「7つの習慣20」で有名なスティーブン・コビーが最初に言い出しました。
それからこの『ビックロック(大きな石)の法則』が生産性オタクの間で大人気になり、現在に至るまで色々なバージョンで語り継がれています。
でもこれを違う角度から見てみましょう。
- 大きい瓶:人生
- 大きな石:家族や友達、健康などの「1番大切なもの」
- 小石:家や仕事などの「ある程度大切なもの」
- 砂:それ以外の些細なもの
もし砂を先に入れると、大きい石や小石が入るスペースがなくなります。
これは人生も同じです。
重要じゃないことに時間を使いすぎると本当に大切なものに使う時間がなくなります。
もっと自分の幸せに何が必要なのかを整理してください。
最も大切なものを優先したり、それに時間を使ったりするべきなんです。
世の中は些細なことにあふれています。
些細なことを気にしすぎずに、自分にとってもっと大切なことを優先してください。
幻想を手放す
人生には「今」しか存在しない
私が伝えたいのは、「今」の時間をもっと大切に使いましょう!ということです。
未来志向の人は「いつか何かをしたら」という考え方を持ちやすい傾向にあります。
- いつか仕事が落ち着いたら
- いつか素敵な人に出会ったら
- いつか心理的な問題が解決したら
いつかその時がきたら、初めてリラックスして、当の人生を生きられる。
そう思っている人はとても多いです。
もちろん私も最近までは同じような考え方で日々を過ごしていました。
私も含めて「いつか何かをしたら」という人のマインドの人は、”まだ大事なことを達成していないから、現在の自分が満たされていない”と考えています。問題が解決しさえすれば、人生は思い通りに動き出し、人生に追われることなくゆっくり生きられると思っています。
でもそんな考え方をしていたら、いつまでたっても心や人生が満たされることなんてありません。
なぜならその考え方は「今」を永遠に先延ばしにする考え方だからです。
もし仕事が落ち着いても、もし素敵な人に出会っても、自分にとって理想としていたタイミングが来たとしても、また充実感を先延ばしにするための”別の理由”がいくつも出てくるでしょう。
冒頭でも紹介しましたが、私も前の職場で働いていたときに「もっと学力の高い学校で進学指導をしたい」と思っていました。そのとき思い描いていた理想は「トップレベルの進学校に行く前に2番手、3番手校で働いて、ある程度の授業力をつけてからトップ校にチャレンジしたい」という道筋です。
当時勤務していた学校の偏差値は45~48ぐらいで、さらにその前に勤務していた学校の偏差値は36~38ぐらいです。教員採用試験に合格してから10年ぐらいはそういった学力の生徒を対象にした授業しかしていないのにいきなり偏差値65~68の生徒を相手に授業をするのはかなりの準備不足ですよね。
だからまずは偏差値50~60ぐらいの学校をステップにしたいと考えていました。
いつか偏差値50~60ぐらいの学校に勤務できたら、トップレベルの進学校にチャレンジしよう、って思っていました。
でも教員の人事って、結局は”教育委員会の駒”でしかないとも感じていたので、自分の人生を教育委員会に左右されるんじゃなくて、自分の人生と自分でつかみにいかないといけないと思い「進学指導」ができる国立大学附属高校への転職にチャレンジしました。
そうは言っても「今の状況が苦しくて、やりたいことが出来るタイミングじゃないんだ。」って人のことを否定するつもりはありません。今が苦しく辛かったとしたら、未来に期待するのは自然なことです。
定職についていないフリーターの人が「早く仕事を終えて飲みに行きたい」、「いつかもっと良い仕事につきたい」と考えていても、誰もおかしいとは思いませんが、夢を叶えて弁護士や建築家になった人が報酬もたっぷりもらっているのに、日々の仕事に楽しみを見出せないのは不自然と感じませんか?
なぜ毎日毎日、プロジェクト完成のために、出世するために、もしくは早くリタイヤするために自分の時間を犠牲にしないといけないのでしょうか。
そんな生き方は少しおかしいと思いませんか?
ニューエイジ思想家のアラン・ワッツはこのおかしな現象を次のように批判しています。
教育について考えてみれば良い。まるで詐欺だ。
まだ幼い子供の頃から保育園に入れられる。保育園では幼稚園に行くための準備をしろと言われる。
幼稚園に入ったら1年生の準備。
1年生になったら2年生の準備。
そうやって高校まで行ったら、今度は大学に行く準備だ。
そして大学ではビジネスの世界に出る準備をしろと言われる。……こんな人生、顔の前にぶら下がったにんじんを追いかけるロバみたいなものだ。
誰もここにいない。
誰もそこにたどり着けない。
誰も人生を生きていないんだ。
これを見て心になにかが刺さった人は、もっと「今」を生きることに目を向けてください。
それこそ自分の人生に目を向けるのタイミングが「今」です
「忙しさ」と「出来ないこと」を受け入れる
蒸気機関車が出来てからブロードバンドを活用する現在までたくさんの新技術が高速化をどんどん押し進めてきました。本当なら、私たちの生活には余裕が生まれ、焦らずにゆっくりできる時間が生まれているはずではないでしょうか。
でも多くの人は、もっと早く動くこと、もっと生活を効率化してしまうことに夢中で、これまでに節約できた時間をありがたく感じている人が少ないように感じます。
おかしな現象だと思いませんか?
特にスマホの普及率が高まってから”何かをしていないと不安になる人”が増えている気がします。
電車に乗っていても100%に近い人がスマホで何かをしています。
スマホが普及するまでは電車の中では本を読んでいたり、Nintendo DSをしたり、友達としゃべっていたり、などいろいろな人がいました。でも今はそういったことをスマホ1台で完結できるためか、ほぼ全員がスマホを触っています。
これは電車に限らず、友達との待ち合わせのときも、飲食店でも同じです。
スマホですべて完結できるために、いつも持っているスマホを触っていないと不安になっているということです。
・友達のSNSが更新されていないか不安になる
・普段忙しいから、スキマ時間を使ってスマホで読書をする
・待ち時間がもったいないから、短時間でできるゲームをする
まさに現代病じゃないでしょうか。
こう考えるとタイパ(タイム・パフォーマンス)みたいな新しい言葉も病的に感じてきますね
何かしていないと不安になるから、その時間を埋めるためにスマホを触る。
不安をコントロールしようとする努力が不安を呼ぶ。
こういう悪意循環に対する理解からアルコール依存症で悩む人たちの有名な洞察が「アルコール打ち負かそうと言う気持ちを完全に手放さない限り、アルコールに打ち勝つことはできない」というものです。
こんな気持になった人は大抵どん底を経験しています。
何をしても自分をごまかせない場所まで落ちたとき、自分の限界という苦しい真実を受け入れざるを得なくなります。そうなってからアルコールを使ってツライ感情を抑えようとするのは無駄なことだったということに気づきます。
ずっと伝えてきたように、すべての細々したことを終わらせて自分がやりたいことに専念するための時間を作ろうというのは現実的ではありません。
- そもそも自分にはすべての細々したことを終わらせる能力なんてない
- 自分の無力さを認めて不可能を可能にすることはできない
こういったことを受け入れたとき、人は実際に実現できることだけに取り組むことができるようになります。まずは現実を直視し、それからゆっくりと、より生産的で充実した生き方に向けて歩きだしてください。
手っ取り早い解決策はありません。不快な感情や痛みからすぐに解放されようとしないで、すべてを解決してくれるような魔法は存在しないという現実をまず受け入れてみましょう
心が豊かになる時間の使い方
みなさんが働いている多くの職場は週休3日制を取っていると思います。最近は働き方改革の観点で週休3日制を導入している企業も出てきました。消防士や警察官などの1.5日勤務したら1.5日休みのような特殊な勤務体系の職場もありますね。
1900年代前半にソ連(旧ロシア)では工場の生産性を高めるために、1週間を7日ではなく5日にし、4日働いて1日休むというシフトが発表されました。ここで重要なのは、常に工場を稼働させるために「みんなが同じ日に休まないこと」が目的だということです。
労働者はA, B, C, D, Eの5つのグループに分けられ、それぞれのグループが違う日に休みを割り当てていたようです。常に4つのグループが工場で働いているようにしていました。
しかしある労働者はソ連の労働組合のような団体が発行している広報誌に勇気ある投稿をしました。
「妻は工場にいて、子供たちは学校に行っていて、家にいても誰とも会えない。
会いに来てくれないなら家で何をすればいいのか、公共のカフェに行くしかないのか。
休日が交代制で労働者が全員一斉に休みにならないというのは、一体どういう生活だ。
一人ぼっちで過ごすなら休日の意味などない」
このソ連の交代制カレンダーは40年近く継続された後、機械のメンテナンスに支障をきたすという理由で廃止されました。
しかし、ソ連政府の実験は時間の価値が量で決まるのではなく、大切な人と過ごせるかどうかにかかっているという真実を実証したのです。
ここで伝えたいのは「みなさんの休日は何のためにありますか?」ということです。
もちろん月曜日から金曜日まで働いた自分の心と身体を休めるため、という回答が多いでしょう。でもそれは裏を返せば、自分の心と身体を休めるために日々仕事をしているということになりませんか?
・推し活をするため
・趣味のお菓子作りをするため
・旅行の計画を立てるため
・やりたかったゲームをするため
休日の過ごし方は個人の価値観なので理由はなんでもOKなんです。ただ、せっかくの休日や仕事を終えたあとの時間ぐらいは心が豊かになる時間の使い方をしてください。
私は「子どもとの時間を過ごすため」と胸を張って言えます
一歩を踏み出すための2つの質問
人生は必ず終わります。
その人生の終わりを意識して自分のやりたいことをして過ごしましょうと伝えてきました。
みなさんも「いろいろなタスクが片付いたらやりたいことをやるんだ」と思っている人も多いと思います。
- もっと自己管理が上手くなったら
- 学位を取得したら
- スキルを身に付けるための十分な修行を積んだら
- 趣味の合う仲間を見つけたら
- 子どもを産んだら
- 子どもが家を出たら
その時こそ何の心配もなく、自分のやりたいことに時間を使うことが出来る、と思っていますよね。でもこれは「”準備が終わる”までは人生が始まらないかのような感覚」じゃないでしょうか。
しかし、現実にはやるべき事はいつだって終わらないし、何かを捨てる事は避けられないし、世界を好きなだけ早く動かすことはできない。どんな経験も痛みを伴わずにうまくいく保証はどこにもない。そして宇宙的な観点から振り返れば、すべては全く意味のないものに終わる可能性が高い。そんな辛い現実を受け入れて何の得があるのかって?
ここにいることができる。人生の本番を生きられる。
限られた時間を本当に大事なことをして過ごせる。
今この瞬間に集中できる。
もちろん長期的な計画を否定するつもりはありません。
上に挙げた例にしても、自己管理をすることも、学位の取得も、スキルを身に付けることも、趣味の合う仲間を見つけることも、子どもを産むことも、子どもを育てることも、どれも大切なことです。ただそういう時間のかかることであっても、「今」この瞬間がなければ始まりません。結果はどうあれ、目の前の一歩にしっかりと取り組むしかないということを自覚してほしいんです。
それが「今」できるすべてなんです
ここでその一歩を踏み出すための2つの質問を紹介します。
○質問1○
生活や仕事の中で、ちょっとした不快に耐えるのが嫌で、楽な方に逃げたりしていませんか?
○質問2○
ありのままの自分ではなく、「あるべき自分」に縛られているのはどんな部分ですか?
質問1について、ある心理学者は人生で重要な決断をするとき「この選択は自分を小さくするかそれとも大きくするか」と自分に問いかけることを勧めています。そのように問えば楽な方に進みたいという欲求に流される代わりに、もっと深いところにある目的に触れることができるからです。
例えば、今の仕事を辞めるかどうか悩んでいるときに、「どうするのが幸せだろうか」と自分自身に問いかけると、楽な方に進んだり、結局は決断できずにズルズル時間だけが過ぎてしまいます。
でも「この選択は自分を小さくするかそれとも大きくするか」と自分に問いかけることで、その仕事を続けることが人間的成長につながるか、それとも続けても何も成長は得られないかと考えれば、答えは自然と明らかになっていきます。
できるなら快適な衰退よりも不快な成長を目指したほうがいいですよね
質問2について、現実から目を背ける人の特徴の1つが「今の生活を”いつかそうなるべき自分”への途中経過」と捉える傾向にあるということです。今が人生本番なのに、その真実から目をそらし、親や世の中の期待に応える自分になるまでは準備段階のつもりでいる人が多くいます。
確かに、いつか正しい自分になれたら、その時は人生がもっと安心で確実なものになるでしょう。でも繰り返しているように、そんな「いつか」は永遠に来ません。
そもそも安心するために誰かに認めてもらおうということ自体が初めから無駄で不要なものだったんです。
なぜ無駄かというと、そもそも人生は”いつも不確かで思い通りにならないから”です。
そしてなぜ不要かというと、誰かに認めてもらうまで自分のやりたいことを待つ必要なんてないからです。
自分の気持ちに素直に従ったり、心が安心するということは、誰かに認めてもらって手に入ることではなく「たとえ認めてもらったとしても安心など手に入らない」という現実を受け入れることから得られます。
誰かに認めてもらわなくても、自分はここにいていい。
そう思えたときに、人は本当の意味で自分らしく生きられるのだと思う。
自分が楽しいと思えることが、最善の時間の使い方かもしれませんね
●まとめ
今回はこのブログのタイトルでもある『限りある人生の過ごし方』についての私なりの考え方を紹介させていただきました。
自分には限界があるという現実を受け入れて、「時間を作る」「時間をコントロールする」という発想を捨てましょう。
この本を読むまでは、いかに効率よく仕事や家事を終わらせて自分の時間を作るか、を考えていました。でも勤務先の学校でも家でもなかなかそういった時間を作ることはできません。
やらなければならないタスクは次から次に沸いてくるし、それを自分なりに仕事を工夫しても周りから「仕事が早い人」と思われて、さらなる仕事が振られるだけです。いつまでたっても自分のやりたいことに専念できる時間は生まれません。そもそも「効率よく仕事や家事を終わらせて自分の時間を作るか」という発想が間違っているということです。
- やりたいことを全部やる時間はない。
- さらには限られた時間の使い方さえも自分ではコントロールできない。
- 時間以外にも体力や才能、スキル、その他いろいろなリソースが足りない。
- すべてを完璧にこなせる人なんていない。
これらの事実を受け入れて、
- 完璧なワーク・ライフ・バランス
- やりたいことがすべて実現できるタイムマネジメント
というようなものは幻想であるという現実を受け入れる必要があります。
人生には「今」しかありません。未来は「今」の連続で出来ています。
- いつか仕事が落ち着いたら
- いつか素敵な人に出会ったら
- いつか心理的な問題が解決したら
いつかその時がきたら本当の人生を生きられると思っている、”いつか何かをしたら”という人のマインドの人は、「まだ大事なことを達成していないから、現在の自分が満たされていないのだ」と考えています。問題が解決すれば、人生は思い通りに動き出し、仕事や人生に追われることなくゆっくり生きられると思っています。
でもそんな考え方をしていたら、いつまでたっても心や人生が満たされることなんてありません。
なぜならその考え方は「今」を永遠に先延ばしにする考え方だからです。
私たちの人生は4000週間で終わります。
40代の人なら残りの人生は2000週間を切っています。
スマホのバッテリー残量でいうと50%を下回っています。
もっと「今」を生きることに目を向けてください。
もっと自分がやりたいことに人生の時間を使ってください。
ということで、限りある人生の過ごし方についての授業を終わります。