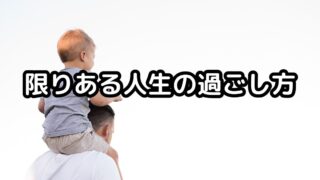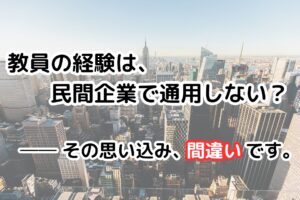どうも!こんにちは、1児の数学教師です。(^o^)/
今から限りある人生の過ごし方についての授業を始めたいと思います。
アメリカで90歳の高齢者を対象にした有名なアンケートがあります。
「90年の人生を振り返って唯一後悔していることは何ですか?」
なんと、これに対して、90%の人が同じ答えでした。
それは、
「もっと冒険(チャレンジ)しておけばよかった」
この回答を聞いてどう感じますか?
みなさんは、今までの人生において色々なことにチャレンジしていますか?
人生におけるチャレンジはスキルアップ的なものもあれば、趣味・娯楽の開拓や健康維持のようなものがあると思います。
・海外旅行に行ってみたい
・自分の好きな仕事をしてみたい
・やりたいビジネスで企業したい
・いろいろな資格取得にチャレンジしたい
・映画鑑賞や読書などの自分の趣味に時間を使いたい
もちろんこれは一例ですが、みなさんは自分のやりたいことにチャレンジしていますか?
先程のアメリカの高齢者を対象にしたアンケート結果から考えると、チャレンジしていない人が多いと思います。
このままチャレンジしない生き方が続いたら5年後、あなたはどうなっていると思いますか?このままチャレンジしない生き方が10年続いたらどうでしょうか?
このままチャレンジしない人生を過ごしたら、人生最後の瞬間に後悔することになりませんか?
あの世にはお金も家具も服も家も持っていくことはできません。
だからこの世で財産を失う事は本当の不幸ではありません。
では、この世の最大の不幸は何だと思いますか?
私は、自分が死ぬ直前に自分の人生に後悔することだと思っています。
死ぬ前に後悔することこそ最大の不幸です。
余談ですが、私は焼肉が好きで、好きな部位はカルビです。
世間的な人気は赤身のハラミですが、私はハラミを食べても物足りなく感じます。
断然カルビです。
しかし40歳を超えてからはカルビを食べられなくなりました。
正確にはカルビは食べられるけど、カルビの脂身によって腹痛を引き起こす体質になってしまった、ということです。
20代の頃のようにカルビの脂身をうまく消化できない身体になってしまったようです。
なぜもっと20代、30代のときにカルビを食べておかなかったのか、とすでに後悔しています。
「今は仕事が忙しいのでしっかりお金を貯めて、退職してから海外旅行に行こう!そして各国の世界遺産巡りをしよう!」
と思っている人もいると思いますが、退職している頃は今のような健康的な身体ではありません。
健康を維持するためにジムに通っていたとしても、30~40代の身体と60~70代の身体は違います。現実として人は老いるのです。
そうやって自分がやりたいこと、チャレンジしたいことを先延ばしにして、自分が死ぬ直前に後悔しませんか?
もちろん老後に世界遺産巡りを実現できる人もいるでしょう。
しかし、アメリカの高齢者を対象にしたアンケート結果をみると、老後になっても何か理由をつけてやりたいことをやらない人が多いんです。
そしてチャレンジしないまま、やりたいことをやらないまま死ぬ直前になって、「もっと冒険(チャレンジ)すればよかった」と後悔します。
”死ぬ前に後悔する”、それを避ける方法があります。
その方法は今この場でしっかり自分の死を想像して、死を真剣に見つめることです。
そうすることでみなさんは自分自身の本心に気づくことができます。
どういうわけか、多くの人は「自分だけは死なない」と思っています。
でも残念ながら私たちが死に至る可能性は100%です。
「おぎゃー」と産声を上げた瞬間から、1秒、1秒、この瞬間にも死に近づいています。
かつて侍たちがあれだけ潔く情熱的に生きられたのは「自分がいつか死ぬ身である」という事実から目をそらさずに「この命を何に使おうか」と日々心を練っていたからです。
死を闇雲に恐れるのではなく、侍たちのように死を受け入れて、死というネガティブな出来事をちゃんと「活用」しませんか?
私は15年以上公立高校の教師として数学を教えていましたが、そのときの働き方に疑問を感じ、国立大附属高校に転職しました。今まで偏差値40未満の学校から偏差値70以上の学校に勤務し、5000組以上の生徒や保護者と関わってきました。子育てや家族のありかたは本当に千差万別です。そういったことを考える中で
- 教師として生徒との向き合い方
- 自分の家族との向き合い方
- 自分の人生との向き合い方
について考えさせられることも多く、「人生には限りがある」という当たり前のことを意識するようになりました。
私はもともと貧乏性でお金に対してケチケチしてるタイプでした。
しかし、結婚して子どもが生まれ、改めて自分の人生計画を見直した結果、家族で思い出を作ることにお金を使いたいと考えました。それからはお金の勉強をスタートし、ファイナンシャルプランナー、簿記などお金に関する資格を取り、NISAで投資をスタートさせました。
また夜間の大学院に通い、自分の教員免許を専修免許にパワーアップさせ、大学院卒の給与体系に移行することに成功しました。
- 給与収入
- 資格手当
- お金の知識
- 配当金
のバランスをとりながら、年々収入を増やすことに成功しています。
今回の授業のテーマは【今すぐ行動するべき、たった1つ理由】についての内容です。
今回は『あした死ぬかもよ?人生最後の日に笑って死ねる27の質問』というひすいこうたろうさんの本を参考にしています。この書籍を読み、それまで自分が考えていたことと一致する部分や新たな気づきを与えてくれた部分を紹介していきたいと思います。
やらない後悔は、やった後悔よりも深く残る
今回の記事でみなさんにお伝えしたいことの結論です。
人はいつ死ぬかはわからない。
だから常に「死」を意識して、死ぬ間際に後悔のない生き方をしましょう。
ということです。
特に冒頭に書いたように、
- なにかやりたいことがある人
- もっとやりたいことがあるけど後回しにしている人
- もっと色々なことにチャレンジしたいと思っている人
は、この記事を読み終わったら(欲を言えば、このページを閉じてでも)すぐに行動に移すべきです。
なぜすぐに行動すべきかの理由は結論でも示したように、人はいつ死ぬかわからないから、です。
「いつかやる」。あなたの「いつか」はいつですか?
江戸時代の平均寿命は約38歳です。
さらに過去にさかのぼって、縄文人の平均寿命も調べてみると、なんと14.6歳だそうです。当時は乳幼児の死亡率がとても高かったのでこれぐらいの年齢になったようですが、それを差し引いても縄文人は平均31歳くらいの寿命だったそうです。
今は31歳で亡くなったら早死にで不幸だと言われます。
だとするなら、縄文人は全員不幸だったということになります。
この世界のただひとつの真実は「生まれたら死ぬ」ということです。
だから死ぬことが不幸なことではないんです。
生きていることが奇跡なんです。
生きている今日という1日が奇跡なのです。
私が大学院に通っていたときお世話になった先生が講義でこうおっしゃっていました。
私たちは命を輝かせながら生きているんです。
そうなんです。
私たちはただ毎日を平凡に生きているように感じるかもしれませんが、私たちが毎日過ごしている1日1日はとても貴重で奇跡のような毎日なんです。
もし「死」がなければ、今日やるべき事は全て明日に回されるでしょう。
そして明日になっても結局ダラダラし、次の日に先延ばしにされると思います。
すべては、「いつか」やるべきことになり、その「いつか」は永遠に来ない。
Monday,Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, …
どこを探しても、1週間の中に「Someday(いつか)」という日はありません。
だから神様は命を完全燃焼させるためのスイッチとして「死」を考えたのです。
命を最大限に輝かせるために「死(締め切り日)」を創造したのです。
締め切りがなければ、宿題もやりませんでしたよね?
「あらゆる仕事が締め切り直前に終わる」
そんな言葉もありますよね。
逆に言えば、締め切り日を自分で設定することで、夢を引き寄せることができます。
夢に”いつまでにやりたいか”という締め切り日を設けるのです。
さて、冒頭の質問です。
「いつかやる」。あなたの「いつか」はいつですか?
いつかやるの「いつか」を「今日」にした日、あなたの運命が変わります。
そして「いつまで」にやり遂げるか。
夢に締め切り日を設けるのです。
お釈迦様の教え
みなさんの人生の満足度は今何点ですか?
私は「今」の時点では70~73点ぐらいかなと思っています。
このままの現状維持でもある程度満足していますが、もう少し満足度の高い人生がいいです。
満足度の平均を50点としたときに、
・自分の満足度は平均点付近
・平均点以下の人生かもしれない…
と思っている人は「人生思い通りにいかない…」って悩んでいませんか?
生きることって大変ですか?
当然です。
お釈迦様は約2500年前「人生は苦 (ドゥッカ:思い通りにいかないもの)である」と悟っています。
- 生まれてくること
- 病気になること
- 老いること
- 死ぬこと
- 大事なこと
は全て思い通りにいかないのが人生です。
でも人生は思い通りにいかないからこそ、面白いんです。
・サッカーが面白いのは手を使ってはいけないから
・ゴルフが面白いのはボールを持って穴に入れてはいけないから
・バレーボールが面白いのはボールを手で持ってはいけないから
横に投げても全部ストライクになるボーリング場があったら行きますか?
「お客様、このボーリング場は、お客様がどこへ投げても全部ピンが倒れるようになっていますので、適当に投げていただいて大丈夫です。」
そんなボウリング場にお金を出していきますか?
思い通りに行ったら人は退屈するだけです。
ゲームの1面ばっかりやっていたら面白くないですよね。
生きるって大変ですか?
大変に決まってるじゃないですか。
大変だからこそ、面白いんです。
大変だからこそ、人は「大」きく「変」わることができるんです。
もう1度聞きますね。
これまでの人生の満足度は今何点ですか?
60点ですか70点ですか?
満足度があと10点上がるとしたら、今と何が違いますか?
10点上がったとしたら、それはあなたが何をしたからだと思いますか?
どんな時間の使い方で、どんな心がけで、どんな習慣を持ったから満足度が上がったのですか?
自分の人生の主人公はあなたです。
自分の人生の満足度を高めるためにも「今すぐ」やりたいことにチャレンジしてみてください。
テキトーに生きていたらあなたの人生がかわいそうですよ
人はいつ死ぬかわからない
生徒の忌引きについて
みなさんは忌引きをどのように意識していますか?
一般的には
忌引:親族や近親者が亡くなった際に、喪に服す(お通夜や告別式の準備)ために休暇を取ること
ですよね。
学校現場でも忌引きで休む生徒がいます。そのクラスの担任でなければ、生徒の欠席理由をすべて把握しているわけではないので、
・風邪などの体調不良で休んでいるのか
・サボりで休んでいるのか
・忌引きで休んでいるのか
はわかりません。(出欠を取ったときに他の生徒が教えてくれることもありますが)
忌引きの場合は後日職員会議での資料に
「忌引 1年△組 ○○○○ (祖父)」などのように教員全体に共有されます。
私に子どもが生まれてからは、生徒の忌引きを特に意識するようになりました。
高校生の忌引理由の対象者は9割ぐらいは祖父母です。
高校生にとっての祖父母というのは当然私たちの両親にあたる存在です。
つまり、私の両親は私の子どもが高校生になる頃になくなっている可能性が高いということです。
私自身の話になりますが、母方の祖父は私が中学校3年生のころに亡くなりました。
祖母は私が社会人になってから亡くなりました。
何歳のときに子どもが生まれるかにもよりますが、人の平均寿命は80歳といわれています。
“20代後半で結婚し、30歳で子どもを生む”というのを1つのサイクルとして考えると
・祖父母が30歳のときに、両親が誕生する。
・30年後、両親が30歳のときに、私たちが誕生する。そのとき祖父母は60歳。
・15年後、私たち15歳、両親45歳、祖父母75歳。
平均寿命が80歳であることを考えると、ちょうど祖父母が亡くなる年齢に近づいています。私の経験からも母方の祖父が亡くなった時期、祖母が亡くなった時期とも合致します。
・さらに15年後、私たちが30歳になり子どもが生まれます。
・そのとき、両親60歳、祖父母90歳。
・私たちの子どもが中高生になる15年後、私たちは45歳、両親は75歳、祖父母は生きていれば105歳。
繰り返しますが、中高生にとっての祖父母というのは私たちの両親にあたる存在です。
このブログを読んでくださっている方に、もしお子様がいらっしゃった場合、その子どもが中高生に近い年齢であれば、あなたの両親の死は確実に近づいています。
かなり失礼なことを書いているという自覚はありますが、これは事実です。
平均寿命80歳というのはあくまでも「平均」なので、90歳を超えても元気な方もいらっしゃいますが、70歳(早ければ60代)で亡くなる方もいらっしゃるということです。
つまり親孝行できるのはあとわずかだということです。
両親に感謝の言葉を伝えていますか?
感謝の気持ちを伝えるなんて「いつでもできる」と思っていませんか?
「いつでもできる」なんて事はこの世に1つもないんです。
だから、気持ちは、今、伝えるしかない。
「ありがとう」「ごめんなさい」「許してください」「愛しています」。
あなたの正直な気持ちを両親に伝えてみませんか?
ある男性のエピソード
「親父にビールを買ってやろう」。
給料日にそう思い、お店でケースを買って来て実家に届けに行きました。
当然親父は喜び、すぐに乾杯、そう思ったのですが、親父の反応は違いました。
「明日からありがたく飲むよ」と。
「なんだよ!今飲まないのかよ」と思いつつ、その日は自分の家に戻ったのですが、翌日仕事中に電話が鳴りました。実家からでした。「親父が進行性の胃がん!?余命3ヶ月?」
もう胃の出口が癌で塞がれていて、栄養はチューブから、となるので即入院とのこと。
「しまった!」
その瞬間、言葉を表すならば、それです。
何も親孝行しないまま「ありがとう」すらまともに言えないまま、親父との時間が終わってしまう……。
その時が来るとすれば、もっと後だ。漠然とそう思っていました。
息子の送ったビールを1口も口にしないまま、その時が来てしまうのか…
「しまった!」今もその言葉でしか表現できません。親父はとても真面目で律儀でしたから、医師の見立てと違わず「余命3ヶ月」、その通りに死にました。その3ヶ月、自分なりに、なりふり構わず、親父の看病はしましたけれども、父を取り戻すことはできなかった。あっという間に永遠の別れがやってきました。
息子としていつかできるいつかやろう、そのうちやろう、そう思ってきたこと、何一つできなかった。どんなに反省しても、どんなに出世しても、どんなに神に祈ってでもできない。そういう「時間の限り」である「いつでもできる」なんて事は、この世に1つもないんだ。やるならば「今」しかない。
やれる事は「今この時」にしかない。
そう全身全霊で学んだのです。痛い位に。
ちなみに最後の一時退院の際、本当に少しだけ私の買ったビールを飲んでくれて「うまいなぁ」といった親父の姿が唯一、少しの救いです。
久しぶりに押し込めていた感情と向き合いました。
泣けました。
時間の大切さを教えてくれる良いエピソードですね。
繰り返しますが、「いつでもできる」なんて事はこの世に1つもないんです。
だから、気持ちは、今、伝えるしかない。
「ありがとう」「ごめんなさい」「許してください」「愛しています」。
あなたの正直な気持ちを両親に伝えてください。
まだその気持ちを十分に伝えていない、あなたの大切な人にも伝えに行ってください。
このままでは必ずそのことを後悔する日が来ますから。
歴史上の偉人(道元)から学ぶこと
中学生の時の歴史の授業で曹洞宗の道元(どうげん)について学習したのを覚えていますか?たぶん鎌倉時代あたりに出てきた人物です。
道元は曹洞宗を開祖したカリスマ禅僧です。
仏教では、どんなに空が曇っていても、雲の上にはいつもお日さまが燦然と輝いてるのと同じように、どんなに悩みという雲で心が覆われていたとしても、すべての人の心には「仏生」が宿っている、という教えがあります。
仏性を辞書で引くと次のようにあります。
仏性:すべての生き物が生まれながらに持っている仏になることのできる性質
すべての人が心の奥で「仏生」を宿しているのに、なぜ社会で成功する人もいれば、成功しない人もいるのだろう。
そこに疑問を持った修行僧がいました。
修行僧はその疑問を師匠の道元に尋ねてみました。
道元の答えは、次のようなものでした。
成功する人は努力する。成功しない人は努力しない。その差だ。
さすが、師匠。明確な答えが返ってきます。
しかし、その夜、その修行僧はまた疑問が湧いてきました。
すべての人はみんな心に「仏性」を宿しているはずなのに、どうして努力する人もいれば、努力しない人もいるのだろう、と。
そこで翌日また道元に尋ねました。
道元の答えはこうでした。
努力する人間には、志がある。努力しない人間には、志がない。その差だ。
道元の答えに弟子の修行僧も納得しました。
しかし、その晩、またまた疑問が湧いてきたのです。
すべての人はみんな心に「仏性」を宿しているはずなのに、どうして志がある人、志がない人がいるのだろう、と。
弟子の修行僧は再び尋ねました。
道元は答えました。
志のある人は、『人間は必ず死ぬ』ということを知っている。志のない人は、『人間が必ず死ぬ』ということを本当の意味で知らない。その差だ。
自分はいつか死ぬ存在であるということを忘れなければ、有頂天になることもなく、物事をいつも正しく判断できるはずです。
あの世には何も持っていけないから
私たちは100年後、この地球いません。
つまり、得たものを全て手放すときがきます。
昨日得たものも、明日得るものも、全て手放す日が来ます。
大切な財布をなくしてしまった?
そんなに落ち込まなくて大丈夫です。
その財布はいつかはなくすものだったんですから。
大切に使っていたスマホが壊れてしまった?
そんなに落ち込まなくて大丈夫です。
そのスマホはいつかは壊れてしまうものだったんですから。
そう考えると、”何かを得ること”が人生ではないことがわかります。
天のむかえが来るその日まで、思いっきり生きること。それが人生です。
財布を落としたら、人は必死に探すのに。
スマホを落としたら、人は必死に探すのに。
自分の本心を忘れても、人は落としたことにすら気づかない。
いつか死ぬであることを胸に刻めば、あなたは自分の本心を思い出す。
本心で生きると、人生は冒険になります
深刻になったら負けです。
最後は骨になるだけです。
人生は1万年もありません。
たかが数十年。
だったら思い切って駆け抜けてみませんか?
みなさんは高校の国語(古典)の時間に『山月記』という物語を学習したのを覚えていますか?
詳しい内容は省略しますが、その物語に出てくる李徴(りちょうという男の言葉を紹介します。
人生は何事をも為さぬには余りに長いが、何事を為すには余りに短い。
簡単に言うと、
人生は何もしないでダラダラするには暇を持て余して長過ぎる。
でも何かを成し遂げようと思うととても短い。
という意味です。
平均寿命が80歳だとして、
80歳 ー(あなたの年齢)=残された人生の年数 です。
健康寿命も考えると残りの人生で、何かを成し遂げるには思うなら、「今すぐ」やりたいことにチャレンジしてください。
ありがとうの対義語
『ありがとう』の対義語(反対の意味)を知っていますか?
・ごめんなさい
・どういたしまして
・嫌い
・無関心
・ばかやろう
などが誤答例にあげられます。
日常的に使っている言葉なのに、対義語を考えると難しいですね。
これは『ありがとう』の意味を考えるとわかります。
『ありがとう』を漢字に変換すると『有り難う』です。
「有る」ことが「難しい」という意味です。
「あるのは難しいこと」「滅多にないこと」「貴重なこと」という意味なんです。
そういった意味の言葉の対義語と考えると、答えがわかりそうですね。
答え:当たり前
私がこれを最初に聞いたときは「なるほど~」と思うのと同時に深く考えさせられました。私たちの日常は当たり前にあふれています。
日常の当たり前についてのエピソードを紹介します。
見えないカップルの人たちは、ずっと相手の顔を触っているそうです。
・相手の顔を1秒でもいいから見てみたい
というのが彼らの夢なんです。
小児がんの病棟にいる子供たちの夢は、
・お父さんとお母さんとラーメン屋に行きたい
・家に帰りたい
・大人になりたい
というものです。
見えること、聞こえること、話せること、歩けること、友達がいること、夜ご飯が食べられること、家に帰れること……。
私たちが日常的に行っているこういった当たり前の行動が出来ないような人たちもいます。
そういった人たちにとって、私たちの毎日は幸せの連続です。
X(旧Twitter)で20代前半で白血病で亡くなった方が生前、こういったポストをしていました。
「やれる可能性があるやつが努力しないのを見ると、胸ぐらをつかんで「俺とかわれ」と言いたくなる」
私も含めてみなさんは、努力や、チャレンジをすることが出来るんです。
テレビも見れる、スマホも触れる、ご飯も作れる、話せる、歩ける、家族がいる。
もう既に幸せに囲まれているんです。
私たちは今、夢のような毎日を過ごしている。
幸せは、未来になるものではなく、今なるものだったのです。
今幸せになれる。
なぜなら、幸せは気づくものだから。
昔の教え子に『幸磨(こうま)』という名前の男子生徒がいました。
名前の由来は「幸せは見つけるものではない。磨くものだ。」というものです。
いい名前ですね。
みなさんも日常の当たり前に感謝しつつ、身近な幸せを磨いてください。
【まとめ】 死を意識することで、人生は動き出す
今回は【今すぐ行動するべき、たった1つの理由】という内容の授業でした。
人はいつ死ぬかはわからない。
だから常に「死」を意識して、死ぬ間際に後悔のない生き方をしましょう。
ということです。
これは私自身に向けて書いた内容でもあります。
ニュースやインターネットなどの報道で毎日のように、事故や殺人によって誰かの死について報じられています。
でも、私も含めたみなさんは、なぜか「自分だけは死なない」と思っています。
そんなことはありません。
「死」は誰にでも平等に訪れます。
いつ死ぬかはわからないだけで。
だから「死」を意識して、死ぬ間際に後悔のないように行動してほしいということです。
行動してほしいというか、行動しなければならないんです。
自分が死ぬ直前になったときに、
- もっと旅行に行けばよかった
- もっと美味しいものを食べればよかった
- もっと好きなことに時間を使えばよかった
- もっと家族との時間を大切にすればよかった
と思いませんか?
このままチャレンジしない人生を過ごしたら、人生最後の瞬間に後悔することになりませんか?
この世の最大の不幸は自分が死ぬ直前に自分の人生に後悔することです。
死ぬ前に後悔することこそ最大の不幸です。
『後悔』とは「『後』になって『悔』やんでも仕方がない」という意味です。
だから「後で」やるのではなく、「今すぐ」行動するべきなんです。
やりたいことがあるなら「今すぐ」チャレンジしてください。
人間は、『やらない(出来ない)言い訳作り』がめちゃくちゃ上手です。
『やらない(出来ない)言い訳作り』をするんじゃなくて、『やる(行動する)理由作り』をしてください。
「あのとき行動してよかった」と思える人生は、自分の手で作れます。
自分の人生の主人公はあなたです。
自分の人生の満足度を高めるためにも「今すぐ」やりたいことにチャレンジしてみてください。
テキトーに生きていたらあなたの人生がかわいそうですよ
最後にもう1度聞きますね。
「いつかやる」。あなたの「いつか」はいつですか?
ということで、限りある人生の過ごし方についての授業を終わります。


.png)

.png)
.png)